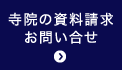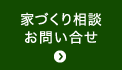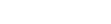2026.2.10
お寺ならではの事情に配慮した住宅(庫裡)のご提案 #外部編 (植松)
2026.2.10
Category: 客殿・庫裡新築
菅野企画設計は、寺院設計、一般住宅、古民家リノベーションを得意としています。
寺院というと本堂を思い浮かべる方が多いと思いますが、
境内の中には本堂だけでなく、書院や客殿、山門、鐘楼、納骨堂や位牌堂など、さまざまな建物が建っています。
そして、職住一体だからこそ欠かせないのが「寺族の住まう家」、
一般的に「庫裡」と呼ばれる建物です。
庫裡をハウスメーカーで建てられるお寺も多いようですが、
単独で成立する一般住宅と違い、お寺は他の伽藍とのつながりがとても大切です。
空いているスペースに型通りの住宅を建ててしまうと、お寺を運営する上で不便が生じてしまうこともあります。
今回は、参拝者の目に触れる「外部側」から見た庫裡の設計ポイントをご紹介します!
◇参拝者に生活感を見せない工夫◇
最近は花粉症で外に洗濯ものを干せない…という方も多いですが、
お寺の場合、参拝者の目に入る場所に洗濯ものを干さないよう、特に気を付けておられる方が多いです。
そのため、庫裡の設計では、物干し場が参拝動線や境内から見えない位置になるよう計画したり、
外観デザインで「物干しスペース」とわからないようにする工夫をしています。

◇外観は他の伽藍との調和が大事◇
使い勝手の面から、他の伽藍と隣接して建てる必要のある庫裡。
そのため、伽藍全体で見たときの調和を大切にしたい、というのは多くの住職さんが望まれるポイントです。
屋根形状や外壁の素材、軒の出など、周囲の建物との関係性を踏まえて計画することで、
庫裡だけが浮いてしまうことのない落ち着いた景観をつくることができます。

一方で、室内は暮らしやすさを重視して現代的にしたい、というご要望も多く、
外観は和風でも、インテリアはモダンやナチュラルテイスト、ジャパンディなどなど。
住まう方のライフスタイルに合わせたご提案を得意としております!
庫裡は「住宅」であると同時に、お寺の景観を構成する大切な建物でもあります。
参拝者からどのように見えるのか、伽藍全体の調和を考えた計画が、
庫裡づくりには欠かせません。
庫裡の新築や建て替え、改修をご検討の際は、ぜひ早い段階からご相談ください!